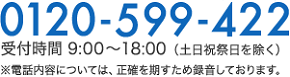- 新卒採用成功ナビTOP
- 新卒採用のノウハウ
- 採用活動において、SNSなどを活用した情報収集はどこまで許されるか?
採用活動において、SNSなどを活用した情報収集はどこまで許されるか?準備する/採用計画

採用活動において、SNSなどを活用した情報収集はどこまで許されますか?
また、どのように付き合っていけばよいでしょうか?
近畿地方にある産業機械メーカーで採用担当をしております。前任担当者が急きょ異動となり、何も分からないまま今年から採用担当となりました。
まだまだ分からないことがたくさんある状況の中、採用活動において、ソーシャル・ネットワークをどの程度活用できるのか、活用してよいのかということが気になっています。
昨今、その使い方が問題となることも多いようですが、対象学生の「生」の情報、面接では分からない本人の素の部分を垣間見ることができるというのは、非常に魅力的に思えます。
一方で、本人の承諾を得ているわけではないので、企業の担当者がその学生について勝手に情報収集することは、あまり好ましいことではないようにも思えます。
ただ、学生の方から、友達申請やフォローをされることもあり、そうなると無視することも難しく、イヤでも相手の情報が眼に入ってきてしまいます。
こうしたSNS上における採用担当者としてのスタンスや情報の取り扱い方について、助言をいただけると非常に助かります。
( 産業機械/従業員規模 1000~3000人未満/採用業務経験 1~2年 )
![]()

人事担当者にとって、ソーシャルメディアはすべて「公の場」と心得ましょう。
人事採用担当者は、人付き合いにおいて完全な公私の区別は難しい と思います。
私は採用の仕事を始めて約20年ほどですが、その間、学生時代からの友人や先輩後輩、採用面接などの仕事で出会った人の区別がどんどんなくなっていきました。
友人が自分の会社に入社してくれたり、かつての同僚と転職してからも私的な付き合いが続いたり、中には採用場面で出会って結局自社に入社してくれなかったような場合でも、10年以上にわたって私的なお付き合いをさせていただいている方もいます。
人を採用するということは、当然ながら、単なる事務手続きではなく、その人と志を同じくする仲間になること、一生涯お付き合いする(同じ会社かどうかは別として)契りを交わすようなものです。
このようなさまざまな人の人生に否が応でも影響を与えざるを得ない人事という仕事についてしまった以上、公私の境がなくなっていくことは仕方ないと思います。むしろ、それが嫌であれば、人事という仕事にはつかない方がよいかもしれません。
そう考えると、人事採用担当者にとって、公私の曖昧なソーシャルメディア上において、明確に公私を分けることは極めて難しいことだと思います。分けることが難しければ、私的なものを公に流すのは非常識となってしまいますから、結局、すべてを「公」とするしかないと思います。
私の例でいうと、Facebookアカウントは会社の電話番号や住所といった「公」のものが載っているもので、会社へ不特定多数の方から、営業電話などがかかってきても仕方ない(問題ない)と考えています。そのため、講演先で知り合った学生などからの「友達申請」なども普通に承認しています。むしろ、名刺交換をするような感覚で、さまざまな告知をするネットワークが広がるわけですので、大歓迎です。
一方、投稿に関していうと、ソーシャルメディアは「公」の場であることを前提として行っています。
例えば、誕生日は載せていませんし、飲み会などのプライベートな写真なども載せません。家族のことはほとんど投稿しませんし、特定の個人や組織を貶めるような発言も行いません。主に、社会に対して信を問いたい意見や、自分の仕事を通じて世の中に提供したいことを慎重な言葉遣いで発信しています。
ちょっと息苦しいかもしれませんが、それも人事の宿命といったら大げさでしょうか。
もちろん、逆にすべてを「私」にしてしまうということもあり得ると思います。
しかし、広くあまねく優秀な人材を日々探すことが仕事である採用担当者が、この上ない人材データベースであるソーシャルメディアを使わないという手はない のではないでしょうか。
最後に、学生のソーシャルメディア上の情報を閲覧する件についてですが、そもそもオープンな場に個々人が自主的に自分の情報を出しているわけですから、それを閲覧しても特段、問題はないと思います。
しかし、人事側から見知らぬ学生に対して、友達申請などを行ってメディア上のリレーションをつくろうとするのは、各メディアのポリシーによってはNGではないでしょうか。
基本的にはリアルで面識のある人とのみ、つながるのがよいと思います。
人事採用担当者は、人付き合いにおいて完全な公私の区別は難しい と思います。
私は採用の仕事を始めて約20年ほどですが、その間、学生時代からの友人や先輩後輩、採用面接などの仕事で出会った人の区別がどんどんなくなっていきました。
友人が自分の会社に入社してくれたり、かつての同僚と転職してからも私的な付き合いが続いたり、中には採用場面で出会って結局自社に入社してくれなかったような場合でも、10年以上にわたって私的なお付き合いをさせていただいている方もいます。
人を採用するということは、当然ながら、単なる事務手続きではなく、その人と志を同じくする仲間になること、一生涯お付き合いする(同じ会社かどうかは別として)契りを交わすようなものです。
このようなさまざまな人の人生に否が応でも影響を与えざるを得ない人事という仕事についてしまった以上、公私の境がなくなっていくことは仕方ないと思います。むしろ、それが嫌であれば、人事という仕事にはつかない方がよいかもしれません。
そう考えると、人事採用担当者にとって、公私の曖昧なソーシャルメディア上において、明確に公私を分けることは極めて難しいことだと思います。分けることが難しければ、私的なものを公に流すのは非常識となってしまいますから、結局、すべてを「公」とするしかないと思います。
私の例でいうと、Facebookアカウントは会社の電話番号や住所といった「公」のものが載っているもので、会社へ不特定多数の方から、営業電話などがかかってきても仕方ない(問題ない)と考えています。そのため、講演先で知り合った学生などからの「友達申請」なども普通に承認しています。むしろ、名刺交換をするような感覚で、さまざまな告知をするネットワークが広がるわけですので、大歓迎です。
一方、投稿に関していうと、ソーシャルメディアは「公」の場であることを前提として行っています。
例えば、誕生日は載せていませんし、飲み会などのプライベートな写真なども載せません。家族のことはほとんど投稿しませんし、特定の個人や組織を貶めるような発言も行いません。主に、社会に対して信を問いたい意見や、自分の仕事を通じて世の中に提供したいことを慎重な言葉遣いで発信しています。
ちょっと息苦しいかもしれませんが、それも人事の宿命といったら大げさでしょうか。
もちろん、逆にすべてを「私」にしてしまうということもあり得ると思います。
しかし、広くあまねく優秀な人材を日々探すことが仕事である採用担当者が、この上ない人材データベースであるソーシャルメディアを使わないという手はない のではないでしょうか。
最後に、学生のソーシャルメディア上の情報を閲覧する件についてですが、そもそもオープンな場に個々人が自主的に自分の情報を出しているわけですから、それを閲覧しても特段、問題はないと思います。
しかし、人事側から見知らぬ学生に対して、友達申請などを行ってメディア上のリレーションをつくろうとするのは、各メディアのポリシーによってはNGではないでしょうか。
基本的にはリアルで面識のある人とのみ、つながるのがよいと思います。